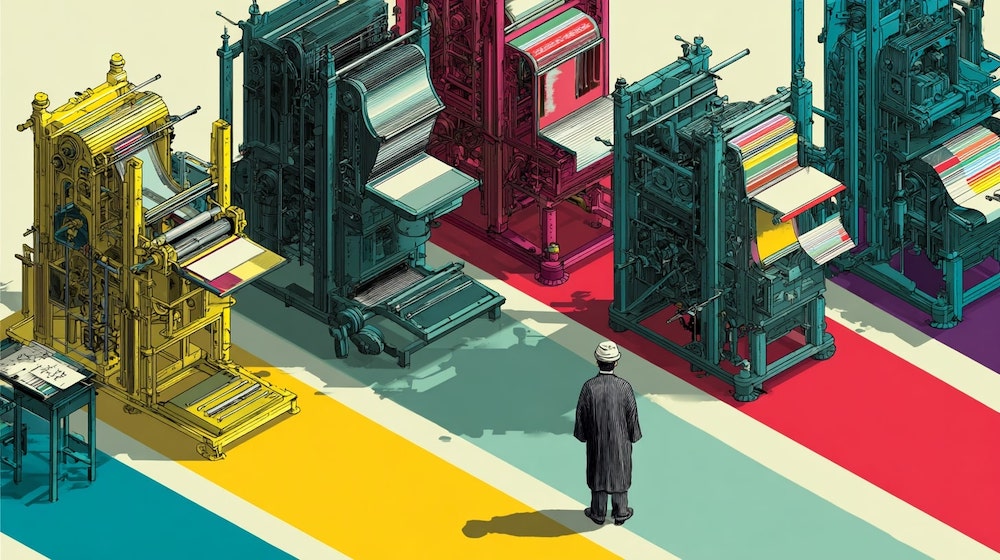「お父さんの仕事って、正直もう時代遅れじゃないの?」。
中学2年になったばかりの息子が、夕食の席でポツリと漏らした一言でした。
悪気がないのは分かっています。
スマホで何でもできる時代に、インクと紙の匂いがする工場を毎日守っている父親の姿は、彼の目にはそう映るのでしょう。
頭では理解できても、グサリと胸に突き刺さった言葉が、その日はずっと抜けませんでした。
はじめまして。
埼玉県で、父が創業した小さな印刷会社を継いだ、田中健一と申します。
リストラを機に30歳でこの世界に飛び込み、今年で12年。
従業員とその家族の生活を背負い、資金繰りに頭を抱え、それでも「この仕事には価値がある」と信じて走り続けてきました。
息子の一言は、私に改めて問いを突きつけました。
「印刷業は、本当に“オワコン”なのだろうか?」と。
この記事は、42歳の中小企業経営者である私が、息子の言葉をきっかけに、印刷業界の「今」と「未来」を真正面から見つめ直した、葛藤と希望の記録です。
同じように時代の変化のなかで奮闘する経営者の方、そして、私たちの仕事の未来を担う若い世代の方に、何か一つでも伝わるものがあればと願っています。
目次
「時代遅れ」と言われた瞬間に感じたこと
息子との会話が突きつけた現実
それは、ごく普通の平日の夜でした。
反抗期真っ只中の息子・大輝(ひろき)とは、最近会話も減りがちです。
その日、珍しく学校の話をしてくれたのが嬉しくて、つい私自身の仕事の話をしてしまいました。
「今日も新しい機械のことで、職人の佐藤さんとずっと話しててな…」
その時です。
スマホに目を落としたまま、大輝が言いました。
「ふーん。でもさ、今どき紙とか使わないでしょ。お父さんの仕事って、正直もう時代遅れじゃないの?」
空気が、一瞬止まったように感じました。
傷つきながらも湧き上がった父親としての想い
ショック、でした。
正直に言うと、かなり堪えました。
まるで、自分がこれまで必死で守ってきたもの全てを、いとも簡単に否定されたような気がしたのです。
「そんなことない!」と感情的に言い返しそうになるのを、ぐっとこらえました。
ここで怒っても、息子との溝が深まるだけだと分かっていたからです。
その夜、妻には「年頃の男の子なんてそんなものよ」と慰められましたが、なかなか寝付けませんでした。
資金繰りが苦しくて眠れない夜は何度も経験しましたが、この日の眠れなさは種類が違いました。
悔しさと、寂しさと、そして心の奥底から湧き上がってくる「負けてたまるか」という想い。
いつか、息子に「お父さんの仕事はすごいんだ」と、心から思ってもらえるような会社にしたい。
いや、絶対にしてみせる。
暗闇の中で、固く決意しました。
「印刷=オワコン」なのか?という疑問
息子は、デジタルネイティブ世代です。
彼らにとって情報は、スマホの画面に流れてくるのが当たり前。
紙の辞書も引かなければ、手紙も書かないでしょう。
その価値観を否定するつもりはありません。
しかし、本当に「紙」や「印刷」は、終わってしまったコンテンツなのでしょうか。
「手触りのあるものには、信頼が宿る」
これは、先代である父の口癖でした。
デジタル情報が溢れかえっている今だからこそ、物理的な「モノ」として存在し、手に取れる印刷物には、特別な価値があるのではないか。
息子に突きつけられた疑問は、私自身の仕事の価値を再発見するための、スタートラインになったのです。
印刷業界のいま:デジタル化と縮小の狭間で
息子の言葉をきっかけに、私は改めて自分たちが置かれている状況を直視することにしました。
正直に言うと、厳しい現実も多々あります。
印刷物需要の減少と顧客ニーズの変化
これは、業界にいる誰もが肌で感じていることです。
かつては大量に刷られていたチラシやカタログは、WebサイトやSNS広告にその役割を奪われつつあります。
経済産業省の統計を見ても、日本の印刷業界の出荷額は1990年代をピークに、長期的な減少傾向にあるのが現実です。
しかし、需要がゼロになったわけではありません。
ニーズが「変化」しているのです。
- 大量生産から、小ロット・多品種へ
- 画一的なものから、パーソナライズされたものへ
- 単なる印刷から、デザインや企画を含めた提案へ
顧客が求めるものが変わってきている。
この変化に対応できるかどうかが、生き残りの分かれ道だと感じています。
デジタルメディアとの競合
息子が言うように、デジタルメディアは強力なライバルです。
Web広告やSNSは、印刷物に比べてコストを抑えやすく、情報をすぐに届けられるという強みがあります。
一方で、印刷物にはデジタルにはない価値があります。
| 項目 | 印刷メディアの強み | デジタルメディアの強み |
|---|---|---|
| 信頼性 | 修正が難しく、情報が吟味されているため信頼されやすい | 情報の更新が容易 |
| 記憶定着 | 五感に訴え、手元に残るため記憶に残りやすい | 映像や音声で多角的に訴求できる |
| 一覧性 | 全体を俯瞰して見ることができ、情報構造を把握しやすい | 膨大な情報量を格納できる |
| ターゲット | 高齢者層などデジタルに不慣れな層にも確実に届く | 興味関心でターゲティングしやすい |
どちらかが一方的に優れているわけではなく、それぞれの役割がある。
私たちは、印刷物の強みを最大限に活かす方法を考え抜かなければなりません。
生き残るための小ロット・高付加価値化の道
「田中さんのところは、小回りが利くのが良いよね」
これは、取引先からいただく、何より嬉しい言葉です。
私たちのような中小の印刷会社が大手と価格で勝負するのは無謀です。
だからこそ、小ロット・高付加価値の道に活路を見出そうとしています。
例えば、100部だけの特別な記念誌や、1枚1枚に異なるデザインを施した招待状。
あるいは、特殊なインクや紙を使って、思わず触りたくなるような名刺を作る。
手間はかかりますが、お客様の「想い」を形にする仕事には、大きなやりがいがあります。
印刷会社の“役割”はどう変わってきたか?
かつて印刷会社は、依頼されたものを「刷る」のが仕事でした。
しかし今は、それだけでは足りません。
お客様の「伝えたい」という想いを、どうすれば最も効果的に届けられるか。
そのための企画段階から関わり、時にはWebサイトや動画制作といったデジタル施策と組み合わせた提案も行う。
私たちは、単なる「印刷屋」から、お客様のコミュニケーション全体をサポートする「課題解決パートナー」へと変わっていく必要があるのです。
中小印刷会社の現場から見たリアル
ベテラン職人たちの技術と誇り
うちの工場には、道一筋40年のベテラン印刷オペレーター、佐藤さん(58歳)がいます。
私が子供の頃から知っている、父親の右腕だった人です。
彼が機械の微調整をすると、インクの乗りが魔法のように変わります。
その日の気温や湿度を肌で感じ取り、紙のコンディションを指先で見極める。
これは、一朝一夕で身につく技術ではありません。
「社長、この紙は昨日より少し湿気を含んでるから、インクを気持ち固めに練りましょう」
その背中には、この仕事に対する揺るぎない誇りが見えます。
この技術と誇りこそ、うちの会社の宝です。
ファクタリング体験に見る資金繰りの苦悩
綺麗事ばかりではありません。
正直に言うと、会社の経営は常に綱渡りです。
数年前、大口取引先の支払いサイトが延長され、キャッシュフローが急激に悪化したことがありました。
銀行からは追加融資を断られ、従業員の給料日が迫る。
あの時の、心臓を鷲掴みにされるような恐怖は忘れられません。
藁にもすがる思いで利用したのが「ファクタリング」でした。
売掛金を買い取ってもらい、即座に現金化するサービスです。
手数料は正直言って高かった。
でも、あの時ファクタリングがなければ、会社は潰れていたかもしれません。
「従業員の顔を思い浮かべると、どんな手を使っても会社を守らにゃいかんのです」
同じ境遇の経営者なら、この気持ちを分かってもらえるのではないでしょうか。
地域に根ざす企業の強みと弱み
私たちは、地元・所沢市の中小企業や個人事業主のお客様に支えられています。
「田中さんとこなら、無理も聞いてくれるから」と頼りにしていただけることが、何よりの強みです。
一方で、地域の景気に業績が左右されやすいという弱みも抱えています。
だからこそ、お客様一社一社との信頼関係が、私たちの生命線なのです。
Webやデザイン事業への拡張の試み
「時代遅れ」で終わらないために、私たちも新しい挑戦を始めています。
印刷の知識を活かして、Webサイトのデザインや制作を手がけるようになりました。
最初は見様見真似でしたが、今では印刷物とWebサイトを連動させた販促企画を提案できるようになり、お客様にも喜ばれています。
アナログな技術と、デジタルの利便性。
その両方を知っていることが、これからの時代、私たちの新しい強みになると信じています。
「時代遅れ」を逆手に取る発想
「古い」は「信頼」や「安心」に変わることもある
息子は「時代遅れ」と言いましたが、見方を変えれば「歴史がある」ということです。
創業から45年以上、この地で商売を続けてこられた。
それは、先代から受け継いできた「信頼」の証でもあります。
情報が簡単に手に入り、そして簡単に消えていく時代だからこそ、変わらずにそこにある「会社」や、手に取れる「印刷物」が与える安心感は、決して小さくないはずです。
顧客との関係性こそ最大の資産
デジタルマーケティングでは、顧客を「データ」として分析します。
それも非常に重要ですが、私たちはそれだけでは終わりません。
納品のついでに世間話をしたり、お客様のお子さんの成長を一緒に喜んだり。
そうした顔の見える関係性の中から、「じゃあ、今度はこんなの作ってみようか」という新しい仕事が生まれることがよくあります。
この人間的なつながりこそ、AIには決して真似のできない、私たち中小企業の最大の資産です。
若い社員・次世代との共創に未来を託す
最近、新卒で山田君(23歳)という若者が入社してくれました。
彼は、私にはないデジタルネイティブな感覚を持っています。
「社長、このパンフレットにQRコードを付けて、制作の裏側を見せる動画に飛ばしませんか?絶対面白いですよ!」
そんな彼のアイデアに、ベテランの佐藤さんが「ほう、そいつは面白そうだ」と目を細める。
世代の違う社員たちが、お互いの知識や感性を持ち寄って一つのものを作り上げていく。
そこに、私は会社の未来を見出すのです。
田中家の小さな改革:デジタルとアナログの融合
息子の一言以来、我が家でも小さな改革が起きています。
- 息子の意見を聞く会(月1回):息子に「どうすれば印刷会社がカッコよくなるか」をプレゼンしてもらう。
- 工場見学ツアーの企画:娘(小5)の友達を招待し、印刷の面白さを伝えるイベントを計画中。
- 妻(元銀行員)による経営分析:ファクタリングの経験も踏まえ、よりシビアな視点で財務状況をチェックしてもらう。
家族を巻き込みながら、デジタルとアナログの最適な融合点を探る。
これも、私なりの挑戦です。
息子へ伝えたいこと、そして未来へ
「継ぎたい」と思える会社にするために
息子が将来、この会社を継ぐかどうかは分かりません。
それは彼自身の人生ですから、私が強制することではありません。
でも、父親として、経営者として、一つだけ誓っていることがあります。
それは、彼が「この会社を継ぎたい」と万が一思った時に、胸を張ってバトンを渡せるような、誇れる会社にしておくことです。
従業員とその家族を守る覚悟
経営者の仕事は、決断の連続です。
その決断の根っこにあるのは、いつも「従業員とその家族の生活を守る」という覚悟です。
ベテランの佐藤さんにも、若手の山田君にも、それぞれの人生がある。
彼らがこの会社で働いていて良かったと、心から思える場所を作ること。
それが、私に課せられた最大の使命だと考えています。
同じ悩みを抱える中小企業経営者へのメッセージ
この記事を読んでくださっているあなたも、もしかしたら同じような孤独や葛藤を抱えているかもしれません。
時代の変化は速く、一人で抱え込むにはあまりにも重い課題が多すぎます。でも、私たちは一人ではありません。
それぞれの場所で、それぞれの誇りを守るために戦っている仲間がいます。
私のこの失敗だらけの体験談が、あなたの明日への一歩を、少しでも後押しできたなら幸いです。
印刷業は“なくならない”、変わるだけ
結論として、私は「印刷業は“なくならない”」と確信しています。
ただし、形は変わっていくでしょう。
ただ刷るだけではない。
お客様の想いに寄り添い、課題を解決し、デジタルと融合し、新しい価値を創造していく。
その変化に対応できた会社だけが、未来へと続いていくのだと思います。
まとめ
息子に「時代遅れ」と言われたあの日から、私の頭の中では様々な考えが駆け巡りました。
- 息子の一言は、時代の声を代弁していたのかもしれない。
- 印刷業界が厳しい状況にあるのは紛れもない事実だ。
- しかし、「古い」ことの中には「信頼」や「技術」という価値がある。
- デジタルとアナログを融合させ、顧客の課題を解決するパートナーになることが未来への道だ。
- 何より、従業員と、そして息子の世代に誇れる仕事をしていく覚悟が重要だ。
「時代遅れ」という言葉は、終わりを告げる宣告ではありません。
それは、新しい時代に適応するための「変化の始まり」を告げる、号砲なのだと今は思っています。
最後に、この記事を読んでくださったあなたに問いかけたいと思います。
あなたの業界は、あなたの仕事は、本当に“終わって”いるのでしょうか?